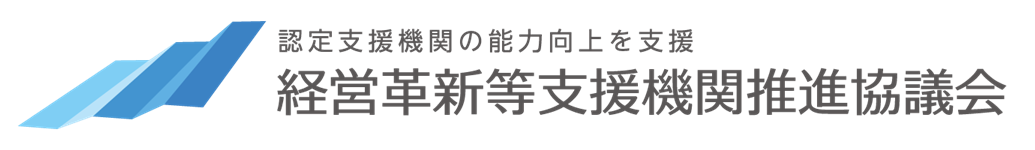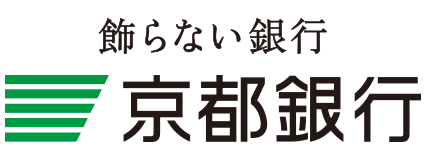「会社法」には「事業年度」に関する定義はなく、「事業年度」に関する定義は「法人税法」に定められています。
(事業年度の意義)法法13
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
清算
平成18年の会社法施行前は「商法」に会社に関する法令が含められていました。その「商法」には、「解散」後の事業年度に関する規定がありません。法人税法に規定される「みなし事業年度」に関する規定を適用していたのです。
(みなし事業年度)法法14
次の各号に規定する法人・・・が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
一 内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間・・・
平成18年の会社法施行後は、「清算事務年度」という1年にわたる期間が定義され、事業年度として適用されることとなりました(会社法494条)。この規定が、法人で違法第13条の「法令で定めるもの」となり、解散の場合も法人税法第13条が適用されることとなったのです。
「事業年度開始の日から解散の日までの期間」は以前と同様ですが、その後の事業年度は「解散の翌日から1年の期間」となります。
(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)法基通達1-2-9
株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。
(貸借対照表等の作成及び保存)会法494
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
破産
破産に関する手続きを定めた「破産法」には事業年度の定めがありません。破産手続の決定により解散すると、その日をもって一旦事業年度を区切ります(法人税法基本通達1-2-9)。
「破産手続開始の決定により解散した場合」には、会社法上「清算すべき場合」から除外されています(会社法475条1号括弧書)。
「事業年度開始日~破産開始日」、「破産開始日の翌日~事業年度終了日」が事業年度となり、その後は破産手続が終結するまで定款に定められた事業年度が続くことになります。
(清算の開始原因)会法475
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由[合併]によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) ・・・